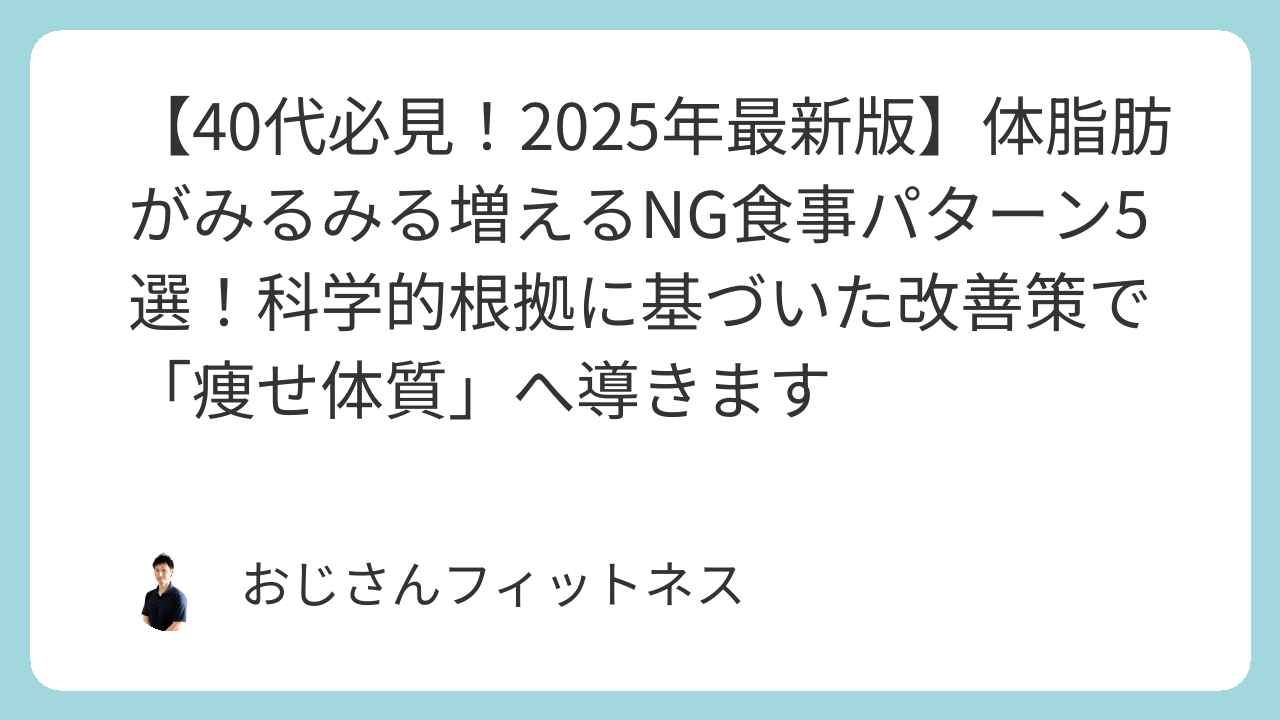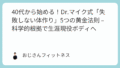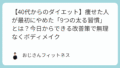【40代必見!2025年最新版】体脂肪がみるみる増えるNG食事パターン5選!科学的根拠に基づいた改善策で「痩せ体質」へ導きます
「若い頃と同じように食べているのに、なぜかお腹周りの脂肪が落ちにくくなった…」
「ダイエットを頑張っているつもりなのに、体脂肪が一向に減らないどころか、むしろ増えている気がする…」
「健康情報はたくさんあるけど、どれが本当に自分に合っていて、効果があるのか分からない…」
40代を迎え、このような悩みを抱えている方は少なくないのではないでしょうか? 体の変化を感じやすくなるこの時期、これまでのやり方では通用しなくなってきたと感じるのも無理はありません。巷には様々なダイエット情報が溢れていますが、中には科学的根拠が乏しいものや、短期的な効果しか得られずリバウンドを招きやすいものも多く存在します。
ご安心ください。 あなたが体脂肪を減らせずにいる原因は、もしかしたら無意識のうちに続けてしまっている「NGな食事パターン」にあるのかもしれません。
この記事では、体脂肪を増やしてしまう5つのNG食事パターンを、40代以降の体の変化や科学的な根拠を交えながら徹底的に解説します。
なぜこれらの食事がNGなのか、そのメカニズムを理解することで、あなたはもう根拠のない情報や誇大広告に惑わされることはありません。 さらに、それぞれのパターンに対する具体的な改善策もご紹介しますので、今日からすぐに実践に移すことができます。
この記事を最後まで読めば、あなたは以下のことを得られます。
-
なぜ自分の体脂肪が減らないのか、その原因となっている可能性のある食習慣が明確になります。
-
体脂肪を増やすNG食事パターンの具体的な内容とその科学的な理由を理解できます。
-
明日から実践できる、健康的で持続可能な食事改善策を知ることができます。
-
正しい知識に基づき、自信を持って40代からのボディメイクに取り組むことができます。
さあ、一緒に「太りやすい食事の罠」から抜け出し、健康的で理想的な体を目指すための第一歩を踏み出しましょう!
まず知っておきたい!40代からの「正しいダイエット」の定義
NGパターンを解説する前に、非常に重要な前提についてお話しさせてください。それは「正しいダイエット」とは何か、という定義です。
多くの方が「ダイエット=体重を減らすこと」と考えていますが、それは必ずしも正しくありません。特に40代以降のボディメイクにおいて目指すべき「正しいダイエット」とは、
「筋肉量を維持、または増やしながら、余分な体脂肪だけを減らすこと」
です。
なぜこれが重要なのでしょうか?
例えば、食事量を極端に減らして体重が5kg減ったとします。しかし、その内訳が体脂肪3kg、筋肉2kgだったらどうでしょうか? 体重は減りましたが、体を支え、代謝を高く保つために不可欠な筋肉まで失ってしまっています。筋肉が減ると基礎代謝(何もしなくても消費されるカロリー)が低下するため、以前よりも痩せにくく、リバウンドしやすい体になってしまうのです。
逆に、筋トレなどを取り入れて体重が2kg増えたとしても、その内訳が筋肉3kg増、体脂肪1kg減であれば、これは紛れもなく「正しいダイエット」であり、ボディメイクの成功と言えます。見た目は引き締まり、代謝も上がってより健康的になっているはずです。
この「筋肉を減らさずに、体脂肪を減らす」という大原則をしっかりと頭に入れて、これから解説するNG食事パターンを見ていきましょう。
【NGパターン1】超低カロリー食:良かれと思って…が招く代謝低下とリバウンド地獄
「とにかく摂取カロリーを減らせば痩せるはず!」そう考えて、1日の摂取カロリーを極端に少なく設定していませんか? 例えば、基礎代謝が1500kcal程度あるにも関わらず、1000kcal以下、あるいはそれ以下の食事で耐え忍ぶようなダイエットです。
これは、体脂肪を増やしてしまう最も陥りやすい、そして危険なNGパターンの一つです。
なぜ超低カロリー食はNGなのか?
-
筋肉が分解され、基礎代謝が激減する
体は、極端にエネルギー(カロリー)が入ってこなくなると、「飢餓状態」に陥ったと判断します。生命を維持するために、体は自らの筋肉を分解してエネルギーを作り出そうとします。先ほど述べたように、筋肉は基礎代謝の大部分を担っています。その筋肉が減るということは、エネルギー消費量が少ない、つまり「燃費の悪い(=太りやすい)」体になってしまうことを意味します。
例えるなら、車を走らせたいのにガソリンをほとんど入れず、代わりに車のボディやシートを削って燃料にしているようなものです。車はボロボロになり、燃費も最悪になりますよね。 -
体が「省エネモード」になり、痩せにくくなる
エネルギー不足が続くと、体は「これ以上エネルギーを消費しないようにしよう」と、基礎代謝そのものを低下させます。まるで、スマートフォンのバッテリーが少ない時に省電力モードになるのと同じです。最初は体重が減っても、すぐに停滞期が訪れ、同じ超低カロリー食を続けても痩せなくなっていきます。 -
必要な栄養素が不足し、心身に不調をきたす
極端に食事量を減らすと、カロリーだけでなく、体に必要なビタミンやミネラルといった微量栄養素も不足しがちです。これにより、集中力の低下、慢性的な疲労感、肌荒れ、便秘、さらには気分の落ち込みなど、様々な不調が現れる可能性があります。健康的に美しくなるためのダイエットが、逆に心身を蝕んでしまうのです。 -
リバウンドのリスクが極めて高い
超低カロリー食は、精神的にも肉体的にも大きな苦痛を伴います。長期間続けることは非常に困難であり、多くの場合、限界が来てしまいます。そして、我慢の反動で過食に走ってしまうと…どうなるでしょうか?
代謝が落ち切った「省エネモード」の体に大量のカロリーが入ってくるため、エネルギーは消費されずに、そのほとんどが体脂肪として蓄積されてしまいます。しかも、失われた筋肉は簡単には戻りません。結果的に、ダイエット前よりも体脂肪率が高い、リバウンドした状態になってしまうのです。
【対策】適切なカロリー摂取と栄養バランスを
超低カロリー食の罠にはまらないためには、自分に必要なカロリーを知り、それを下回りすぎない範囲で、栄養バランスの取れた食事を摂ることが重要です。
-
自分の基礎代謝量と活動量を知る: まずは、自分の基礎代謝量(生命維持に必要な最低限のカロリー)を知りましょう。ネットで検索すれば計算ツールがたくさんあります。それに加えて、日常生活や運動による消費カロリー(活動量)を考慮し、1日の総消費カロリーを把握します。
-
適切な摂取カロリーを設定する: ダイエット中は、総消費カロリーから300~500kcal程度をマイナスした値を目標摂取カロリーとするのが一般的ですが、極端に減らしすぎないことが肝心です。基礎代謝量を下回る設定は避けましょう。
-
PFCバランスを意識する: カロリーだけでなく、三大栄養素であるタンパク質(P)脂質(F)炭水化物(C)のバランス(PFCバランス)を意識しましょう。特に筋肉の材料となるタンパク質は、体重1kgあたり1.2g〜2.0g程度を目安にしっかり摂取することが、筋肉量を維持する上で非常に重要です。
-
ビタミン・ミネラルも忘れずに: 野菜、きのこ類、海藻類などを積極的に取り入れ、体の調子を整えるビタミンやミネラルもしっかり補給しましょう。
「我慢すればするほど痩せる」というのは大きな間違いです。しっかり栄養を摂り、筋肉を守りながら体脂肪を減らすことこそが、40代からの賢いダイエットなのです。
【NGパターン2】朝食抜き:1日の始まりが「脂肪蓄積モード」へのスイッチに
「朝は時間がないから」「食欲がないから」「ダイエットのためにカロリーを抑えたいから」といった理由で、朝食を抜いていませんか?
忙しい現代人、特に時間に追われがちな40代にとって、朝食をスキップすることは珍しくないかもしれません。しかし、これも体脂肪を溜め込みやすくしてしまうNGパターンなのです。
なぜ朝食抜きはNGなのか?
-
昼食時の血糖値スパイクを招き、脂肪を溜め込みやすくする
睡眠中は何も食べていないため、朝起きた時点の体はエネルギーが枯渇した状態です。そこで朝食を抜いてしまうと、前日の夕食から次の日の昼食まで、15時間以上もの間、エネルギーが補給されないことになります。
当然、昼食時には強い空腹感を感じますよね。そこで一気に食事を摂ると、血糖値が急上昇(血糖値スパイク)します。すると、血糖値を下げるために膵臓からインスリンというホルモンが大量に分泌されます。インスリンは血中の糖を細胞に取り込む働きがありますが、急激かつ大量に分泌されると、糖をエネルギーとして使い切れず、脂肪として蓄積しやすくしてしまうのです。
朝食を抜いた分のカロリーを昼食で摂れば同じ、というわけではありません。食べるタイミングと血糖値の上がり方が、脂肪の蓄積に大きく関わっているのです。 -
エネルギー不足で筋肉が分解される
超低カロリー食と同様に、長時間のエネルギー不足は、体内の筋肉を分解してエネルギーを作り出す「糖新生」という働きを促進してしまいます。朝食を抜くことで、大切な筋肉が失われ、基礎代謝が低下し、太りやすい体質につながる可能性があります。 -
体内時計が乱れ、代謝リズムが悪くなる
朝食は、睡眠中に低下した体温を上昇させ、体の活動スイッチを入れる役割も担っています。朝食を抜くと、この体内時計(サーカディアンリズム)が乱れ、代謝のリズムが悪くなる可能性も指摘されています。
【対策】バランスの取れた朝食で1日の良いスタートを
体脂肪を溜め込まないためには、朝食をしっかり摂ることが大切です。
-
バランスを意識する: 理想は、エネルギー源となる複合炭水化物(玄米、オートミール、全粒粉パンなど)、筋肉の材料となるタンパク質(卵、納豆、ギリシャヨーグルト、鮭など)、そして血糖値の上昇を緩やかにする食物繊維(野菜、きのこ、海藻類など)を組み合わせることです。
-
セカンドミール効果を活用する: 朝食に食物繊維をしっかり摂ると、その次の食事(昼食)の血糖値上昇も緩やかにしてくれる「セカンドミール効果」という嬉しい働きがあります。 野菜サラダや具沢山の味噌汁、オートミールなどを取り入れてみましょう。
-
時間がない時の工夫: どうしても時間がない場合は、プロテインドリンク、ギリシャヨーグルト、バナナ、ゆで卵、納豆ご飯など、手軽にタンパク質とエネルギーを補給できるものだけでも摂るように心がけましょう。インスタント味噌汁に乾燥わかめや刻みネギ、とろろ昆布などを加えるだけでも食物繊維を補えます。
「朝食は1日の食事の中で最も重要」と言っても過言ではありません。食欲がない方も、まずは少量から、何か口にする習慣をつけてみてください。
【NGパターン3】味が濃い食事:「美味しい」の裏に潜む過食とカロリーの罠
「ダイエット中の食事は味が薄くて味気ない…」そんなイメージがあるかもしれませんが、決してそういうわけではありません。美味しいものを食べることは、心の栄養にもなり、ダイエット継続のモチベーションにも繋がります。
しかし、「味が濃い」食事が習慣になっている場合は、注意が必要です。無意識のうちに体脂肪を増やしてしまう原因になっている可能性があります。
なぜ味が濃い食事はNGなのか?
-
ご飯(炭水化物)が進み、糖質過多になりやすい
甘辛いタレ、こってりしたソース、塩気の効いたおかず…。味が濃いものは、白いご飯との相性が抜群ですよね。美味しいと感じる反面、ついついご飯をおかわりしてしまい、糖質の摂取量が過剰になりがちです。糖質は重要なエネルギー源ですが、摂りすぎれば体脂肪として蓄積されます。 -
調味料自体のカロリーが高い場合がある
美味しいと感じる調味料、例えばマヨネーズ、ドレッシング、焼肉のタレ、デミグラスソースなどは、脂質や糖分が多く含まれており、それ自体が高カロリーな場合があります。少量なら問題ありませんが、習慣的にたっぷり使っていると、知らず知らずのうちにカロリーオーバーを招きます。 -
塩分の摂りすぎは「甘いもの」への欲求を招く
フライドポテトのような塩辛いものを食べた後に、甘い炭酸飲料が飲みたくなる経験はありませんか? 塩分の多い食事は、味覚のバランスを取ろうとして、甘いものへの欲求を引き起こしやすいと言われています。濃い味のおかずと甘いデザートやジュースの組み合わせは、カロリーと糖質のダブルパンチになりかねません。 -
早食いにつながりやすい
味が濃く美味しいものは、あまり噛まずに飲み込んでしまう「早食い」につながりやすい傾向があります。食事を始めてから満腹中枢が刺激され「お腹いっぱい」と感じるまでには、通常15分〜20分程度かかると言われています。早食いをすると、満腹感を得る前に必要以上に食べ過ぎてしまうリスクが高まります。
【対策】旨味を活用し、味付けにメリハリを
濃い味付けに慣れてしまっている方は、少しずつ味覚をリセットしていく意識が大切です。
-
「出汁(だし)」の旨味を活用する: 鰹節、昆布、干し椎茸などの出汁には、グルタミン酸やイノシン酸といった「旨味成分」が豊富に含まれています。この旨味をしっかり活用することで、塩分や砂糖、油分を控えめにしても、料理の満足感を高めることができます。旨味を感じると、幸福ホルモンと呼ばれるセロトニンの分泌も促され、精神的な満足感から過食を防ぐ効果も期待できます。
-
香辛料やハーブ、香味野菜を活用する: 唐辛子、胡椒、カレー粉、生姜、ニンニク、ネギ、大葉、ハーブ類などを上手に使うことで、味にアクセントや深みを出すことができます。減塩しても物足りなさを感じにくくなります。
-
「かける」より「つける」: 醤油やソースなどを直接料理にかけるのではなく、小皿に入れて「つけて食べる」ようにすると、使用量を減らすことができます。
-
ゆっくりよく噛んで食べる: 意識して咀嚼回数を増やし、ゆっくり食べることで、満腹中枢が刺激されやすくなり、食べ過ぎを防ぐことができます。食材本来の味や香りも楽しむ余裕が生まれます。
たまには外食などで濃い味のものを楽しむのは良いですが、普段の食事では少し味付けを意識するだけで、摂取カロリーや塩分量をコントロールしやすくなります。
【NGパターン4】高カロリーな飲み物:「飲むカロリー」は油断大敵!脂肪に直結しやすい
食事内容には気を使っているけれど、飲み物についてはあまり意識していない、ということはありませんか? 甘いカフェラテ、果汁100%ジュース、スポーツドリンク、そしてもちろんお酒など…。
これら「高カロリーな飲み物」の習慣的な摂取も、体脂肪を増やす見逃せないNGパターンです。
なぜ高カロリーな飲み物はNGなのか?
-
吸収が早く、血糖値を急上昇させやすい
液体に含まれる糖分は、固形物に含まれる糖分よりも消化・吸収されるスピードが非常に速いのが特徴です。そのため、飲んですぐに血糖値が急上昇しやすく、インスリンの過剰分泌を招き、脂肪として蓄積されやすい状態を作り出してしまいます。(NGパターン2「朝食抜き」のメカニズムと同様です) -
満腹感が得られにくく、カロリーオーバーしやすい
飲み物は、固形物を食べる時のような咀嚼(そしゃく)がないため、満腹感を得られにくいというデメリットがあります。お腹がいっぱいでも、甘い飲み物ならさらに飲めてしまう、という経験はありませんか? 知らず知らずのうちにカロリーを重ねてしまい、1日の総摂取カロリーが大幅にオーバーしている可能性があります。特に、食事と一緒に甘い飲み物を摂る習慣がある方は要注意です。 -
「エンプティカロリー」が多い
清涼飲料水や加糖飲料の多くは、カロリーは高いものの、体に必要なビタミンやミネラル、食物繊維などの栄養素がほとんど含まれていない「エンプティカロリー(空っぽのカロリー)」です。体を満たす栄養にはならず、ただカロリーだけを摂取してしまうことになります。 -
果物ジュースの落とし穴
「果汁100%なら健康的」と思いがちですが、注意が必要です。果物をそのまま食べるのとジュースで摂るのとでは、体に与える影響が異なります。-
食物繊維の損失: ジュースにする過程で、血糖値の上昇を緩やかにしたり、満腹感を与えたりする食物繊維の多くが取り除かれてしまいます。
-
ビタミン・ミネラルの損失: 加熱処理などにより、熱に弱いビタミンなどが壊れてしまうことがあります。
-
糖分の濃縮・添加: 濃縮還元のジュースや、飲みやすくするために砂糖(果糖ブドウ糖液糖など)が添加されているものも多くあります。特に果糖は、摂りすぎると中性脂肪として蓄積されやすいことが指摘されています。
-
【対策】基本は「水」か「お茶」、甘味料にも注意
飲み物からの余計なカロリー摂取を防ぐには、シンプルな選択が一番です。
-
基本の飲み物は「水」か「お茶」にする: 日常的な水分補給は、カロリーゼロの水やお茶(緑茶、麦茶、ほうじ茶、ハーブティーなど)を基本にしましょう。
-
甘い飲み物は「嗜好品」と位置づける: ジュースや加糖コーヒー、炭酸飲料などは、毎日飲むのではなく、特別な時の「ご褒美」や「嗜好品」として、頻度や量を決めて楽しむようにしましょう。
-
「無糖」を選ぶ習慣を: コーヒーや紅茶は無糖を選ぶ、あるいは甘味料を少量にするなど、意識的に糖分を減らす工夫を。
-
果物は「そのまま」食べる: 果物の栄養を効率よく摂るなら、ジュースではなく、食物繊維やビタミンが豊富な生の果物をそのまま食べるのがベストです。
-
スポーツドリンクは必要な時に: 大量に汗をかく運動時や脱水症状が懸念される時以外は、日常的な飲用は糖分の摂りすぎにつながる可能性があります。
-
アルコールは量と頻度を考える: アルコール自体にもカロリーがあり、食欲増進効果もあるため、飲み過ぎは禁物です。休肝日を設け、飲む量や頻度をコントロールしましょう。
飲み物は、食事以上に無意識に口にしていることが多いものです。一度、自分が1日に何をどれだけ飲んでいるか見直してみると、意外な発見があるかもしれません。
【NGパターン5】習慣化している食事:「なんとなく」食べが脂肪を育てる
「特に食べたいわけじゃないけれど、デスクにお菓子が置いてあるからつい手が伸びる」
「テレビを見ていると、口寂しくてポテトチップスを開けてしまう」
「食後には必ずデザートを食べないと落ち着かない」
このように、強い食欲があるわけではないのに、「なんとなく」「いつもの習慣だから」という理由で食べてしまっているものはありませんか? これも、体脂肪をじわじわと増やす原因となるNGパターンです。
なぜ習慣化している食事はNGなのか?
-
必要以上のカロリーを摂取している可能性がある
本当に体がエネルギーを必要としているわけではなく、ただの習慣で食べている場合、それは体にとっては余分なカロリーとなります。特に、高カロリーなスナック菓子や甘いデザートなどが習慣になっている場合、その積み重ねは無視できません。 -
「心の栄養」になっていない可能性がある
本当に食べたくて、それを食べることで幸せを感じたり、ストレスが解消されたりするのであれば、それは「心の栄養」として意味があるかもしれません(もちろん、頻度や量には注意が必要ですが)。しかし、「なんとなく」の習慣で食べているものは、食べた後に満足感よりも罪悪感を感じたり、「また食べちゃった…」と後悔したりすることはありませんか? それは、体にも心にもあまり良い影響を与えていない可能性があります。 -
「もったいないカロリー」になっている
よくよく考えてみれば「そこまで食べたいわけではなかった」のに、習慣だからという理由で摂取したカロリーによって体脂肪が増えてしまうのは、非常にもったいないことです。その分のカロリーを、もっと栄養価の高いものや、本当に食べたいものに使う方が、よほど有意義だと言えるでしょう。
【対策】自分の食習慣を客観視し、「なんとなく」をやめる
このNGパターンから抜け出すには、まず自分の食習慣を意識的に見直すことが重要です。
-
「本当に食べたい?」と自問する: 何か口にしようとした時、一呼吸おいて「今、本当にお腹が空いているかな?」「これを本当に食べたいと思っているかな?」と自分に問いかけてみましょう。
-
食べる状況や感情を記録してみる(レコーディング): いつ、どこで、誰と、どんな気持ちの時に「なんとなく」食べてしまうのかを記録してみると、自分の食行動のパターンが見えてきます。例えば、「仕事でストレスを感じると甘いものを食べたくなる」「手持ち無沙汰になるとスナック菓子に手が伸びる」など、きっかけが分かれば対策も立てやすくなります。
-
代替行動を見つける: 口寂しさやストレスから「なんとなく」食べてしまう場合は、食べる以外の代替行動を見つけましょう。例えば、ガムを噛む、温かいハーブティーを飲む、席を立って軽くストレッチをする、散歩に出かける、好きな音楽を聴くなどが考えられます。
-
ストックを置かない・視界に入れない: 家や職場に「なんとなく」食べてしまうお菓子などのストックを置かない、目につく場所に置かない、という物理的な対策も有効です。
-
マインドフル・イーティングを試す: 食べる時は、スマホやテレビを見ながらの「ながら食べ」をやめ、目の前の食事に意識を集中し、色、香り、食感、味を五感でじっくり味わう「マインドフル・イーティング」を試してみましょう。満足感が高まり、「なんとなく」食べを防ぐ効果が期待できます。
この「習慣化している食事」の見直しは、意外と簡単に、そして効果的に摂取カロリーを減らせる可能性があります。「これをやめるだけで体脂肪が減り始めた!」ということも十分にあり得ますので、ぜひ一度、ご自身の食習慣を振り返ってみてください。
まとめ:NGパターンから抜け出し、理想の体へ
今回は、40代以降の方が陥りやすく、体脂肪を増やしてしまう原因となる5つのNG食事パターンとその対策について詳しく解説しました。
【体脂肪を増やすNG食事パターン5選】
-
超低カロリー食: 筋肉減少、代謝低下、栄養不足、リバウンドを招く。
-
対策: 適切なカロリー摂取、PFCバランス、微量栄養素の確保。
-
-
朝食抜き: 血糖値スパイク、脂肪蓄積、筋肉分解、体内時計の乱れ。
-
対策: バランスの取れた朝食、セカンドミール効果活用。
-
-
味が濃い食事: 過食、カロリーオーバー、塩分過多、甘いもの欲求。
-
対策: 出汁や香辛料の活用、減塩、ゆっくり食べる。
-
-
高カロリーな飲み物: 吸収が早く血糖値急上昇、満腹感なし、無意識のカロリー摂取。
-
対策: 水・お茶中心、無糖選択、果物はそのまま食べる。
-
-
習慣化している食事: 必要以上のカロリー摂取、「なんとなく」食べによる脂肪蓄積。
-
対策: 食習慣の見直し、本当に必要か自問、代替行動。
-
NG食事パターンと対策法のまとめ表
| NG食事パターン | なぜNGなのか? | 対策法 |
| 1. 超低カロリー食 | 筋肉減少、基礎代謝低下、栄養不足、リバウンドしやすい | 適切なカロリー摂取(基礎代謝以上)、PFCバランス重視(特にタンパク質)、微量栄養素確保 |
| 2. 朝食抜き | 血糖値スパイク、脂肪蓄積促進、筋肉分解、体内時計の乱れ | バランスの取れた朝食(タンパク質、複合炭水化物、食物繊維)、セカンドミール効果活用 |
| 3. 味が濃い食事 | 過食、カロリーオーバー、塩分過多、甘いものへの欲求、早食い | 出汁や香辛料・ハーブの活用、減塩(つける食べ方など)、ゆっくりよく噛む |
| 4. 高カロリーな飲み物 | 吸収が早く血糖値急上昇、満腹感なし、無意識のカロリー摂取、エンプティカロリー | 水・お茶中心、無糖選択、果物はそのまま食べる、アルコールは適量に |
| 5. 習慣化している食事 | 必要以上のカロリー摂取、「なんとなく」食べによる脂肪蓄積、心の栄養不足 | 食習慣の客観視(レコーディング)、本当に食べたいか自問、代替行動、ストック管理、マインドフル・イーティング |
もしかしたら、「自分は複数のパターンに当てはまる…」と感じた方もいらっしゃるかもしれません。しかし、焦る必要はありません。 すべてを一度に変えようとするのではなく、まずは一番改善しやすそうなパターン一つから手をつけてみましょう。
大切なのは、正しい知識を身につけ、ご自身の体と向き合いながら、無理なく続けられる方法を見つけることです。そして、「筋肉を維持・増加させながら、余分な体脂肪を減らす」という正しいダイエットの原則を忘れないでください。
この記事が、あなたの40代からのボディメイクを成功させるための一助となれば幸いです。正しい知識と少しの工夫で、体は必ず変わっていきます。自信を持って、理想の体を目指しましょう!
もっと詳しく知りたい!専門家から直接アドバイスを受けたい方へ
「一人ではなかなか続けられない」という方には、オンラインでのパーソナルサポートもおすすめです。あなたの目標やライフスタイルに合わせた、最適なプランを一緒に考え、伴走します。
▶ オンラインパーソナル(ココナラ)はこちら!
https://coconala.com/users/3522116
正しい知識を力に変えて、理想の体を手に入れましょう!